イタロ・カルヴィーノ『冬の夜ひとりの旅人が』の読書録
《イタロ・カルヴィーノ(著)、脇功(訳)(1981)『冬の夜ひとりの旅人が』松籟社》の読書録です。
イタロ・カルヴィーノ『冬の夜ひとりの旅人が』のあらすじ
本著の大まかなあらすじは、本著と同名の本を買い求めて読み始めると、装丁の問題があって読み進められない。書店に抗議にいくと、同様に本の続きを求めて女性客が訪れていた。主人公はその本をきっかけに彼女と懇意になりたいと思い話しかけ、書店が正しいものとして取り替えてもらった本の感想を話し合おうと約束し連絡先を交換した。ところが次の本の装丁にも問題があり、主人公は彼女と正常に一貫した小説を求めてあちこちを巡ることになる。
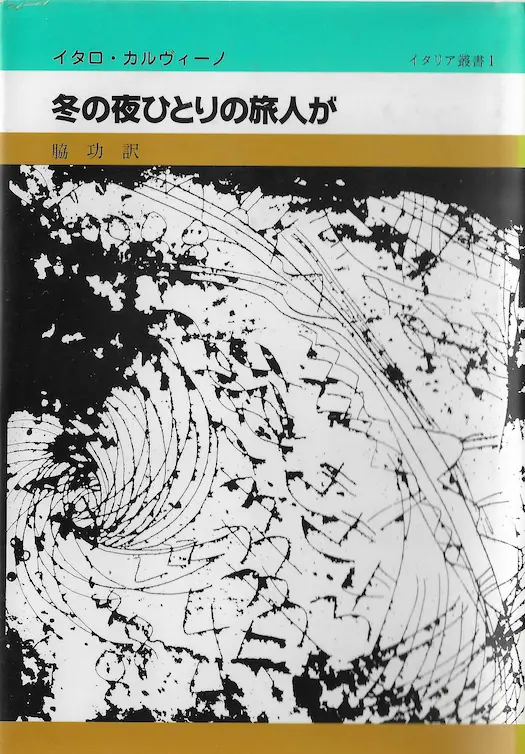
こうして書いてみると、小説らしいストーリーが展開されているように見えるが、実際にはこの小説を構成する要素をかなり省いており、この粗筋から想像される内容とは程遠く、普通の物語として感想を書くことの難しさがわかる。
メタ構造と読者の同一化
この作品を構成する要素とは、まずあらすじだけでも2点挙げた正常に製本されていない小説だが、それぞれ主人公が読んだ分は、掲載や引用の形ではなく、そのまま章を分けるような形で書かれており、いわば画中画の要領で入れ子構造になっている。各章はその小説の断片を挟んで切り替わるようになっている。
それら断片はいずれも別々の架空の作者の手によるものであり、実はそれら小説はいずれもそのタイトルが示すものとは全く別の本を翻訳したものであることが徐々に分かっていく。各断片の内容は本筋とは全く関係のないもので、それひとつずつが普通の小説の体裁を持っており、ちゃんとした小説になっている。主人公たちはバラバラの断片のそれぞれの小説に惹かれるが、別の小説の断片ばかりにたどり着いてしまう。
この画中画のような構造が意図するものは、メタ的な視点を浮き彫りにすることにあると思われる。主人公と読者は構造上同一となる。
この主人公と読者を同一化しようとする試みは他でも見られる。作中語り手が、主人公を男性読者、主人公が出会った女性を女性読者と呼称し、また「あなた」と呼称することからも見て取れる。実際、それを志向している、という旨も語り手自身もはっきり述べる。
語り手の存在と読書体験の揺さぶり
この語り手によるメタ的な発言が、作中で何度も読者に語りかけることも、この小説の一つの構成要素となっている。読者は小説のストーリーに自然と没入することは許されず、入り込もうとするたびに肩を掴んで揺すり起こされ、「今読者はどういう状態でどう思っておりこれからどうしたいのか」を読者の感覚を上書きして再定義しようとする。読者を、男性読者あるいは女性読者として作品の一部として組み込み、くくりつけようとする意図があるように感じる。
結果的に、この本を通常の小説として読むことはかなり困難であり、普通の読書感想もまた困難である。
では、なぜ作者は読者を作中の主人公と同一化して感情や行動を制限し、制限されていないことに注目させるのか。それとも制限されるフラストレーションによって不可思議な感覚を与えるためか。あるいは、読書の自由を奪うことで、読書が何たるかを思い起こさせ、読書の喜びを回帰させるためか。それともそれら全てなのか。
第11章:読書観の対立
第11章では男性読者自身の口から「どういった本が好きなのか」が語られる。ここは、少し文脈的にズレている。というのも、その場にいる他の人物たちが読書とは何か、読書に何を求め、読書は何を齎すかについて話している一方で、男性読者は「本としてそれ1冊で完結しており、その本の細部はその本の全体に帰結する」、つまり普通考えられるような通常の筋、展開を持つ本が好きである、といったようにテーマの抽象度が他の読者と違っていて話が噛み合っていないからだ。
すると周りの読者は、それは当たり前だと言い、物語は究極的に、生命の連続性と死の不可避性の二面性を持って終わる他ない、という。そうした中で、男性読者は、女性読者との結婚を決心する。
最終章では、結婚後二人がベッドで本を読み、男性読者はイタロ・カルヴィーノの本を読み終える、といった結びになっている。
体裁へのこだわりとその皮肉
第11章で男性読者は「本は体裁的にこうあってほしい」と話しているが、他の読者は「読書から得られる感覚的な話」をしている。終わりを求めることも、本来あるはずの体裁を求めることと同義であり、他の読者からすると、体裁的にはお決まりなのだから、体裁にこだわることは無益だと言いたいのかもしれない。
その後の突拍子もない、男性読者の結婚への決意は、体裁に拘泥する人への皮肉とも捉えられる。
その他の登場人物たちの意味
ところで、実際のところここまでの考察はその他の要素を全く無視している。女性読者ルドミッラと、翻訳者マラーナ、作家のフラナリー、他の登場人物。彼らは各々明らかな動機を持っていて、いかにも含蓄がありそうに思えてくる。
小説という形式への懐疑
体裁に拘る必要がないのであれば、体裁にこだわることは無益であるという主張も取るに足りないということになる。どうも一筋縄ではいかない。構造全体が、小説の目的を証明する行為を否定しているようだ。